ChatGPTのようなAIとの対話が日常化するなかで、人間の「社会的欲求」そのものが変化し始めています。
この記事では、AI時代における承認欲求と、つながりの形の変化、そして「理論型社会」から「感情型社会」へと移行する現代の流れを伝えています。
ChatGPTの普及で社会的欲求はどう変わったか?
かつての社会的欲求の主な特徴とは
人は「誰かに認められたい」「共感されたい」と思ったとき、リアルの人間関係に依存していました
しかしSNSの普及によって、より加速している面もあるでしょう。しかし、そこには摩擦や不安・不満が伴うことも、しばしばあります。
AIがもたらした“新しいつながり”の形
ChatGPTのようなAIに「丁寧に反論されず、自分の話を聞いてもらう」ことが当たり前になる中で、感情を安心して預けられる相手としてAIを活用する人が増加中です。
これは、社会的欲求の“満たし方”が変わりつつある兆候とも言えます。
「理論型社会」から「感情型社会」への変化とは?
なぜ今、論理より“感情”が重視されるのか
情報過多な現代では、「何が正しいか」「どんな価値があるか」よりも「誰の言葉か」「どう語られているか」「どんな雰囲気の人か」が重視される傾向があります。
つまり、共感性や語りのトーンといった“感情的な質”が人の意思決定を左右するようになっているのです。
AIが論理を担う時代に、人間に求められるもの
AIは論理や情報整理を得意とします。仕事において管理の殆どはAiで置き換えられていくでしょう。それでは人間に求められるものは何でしょうか?
それは、感じ取る力・共鳴する力・問いかける力など、論理を超えた「感情知性」です。
「共感」から始まる、新しい人間関係
感情の言語化が価値になる時代
私たちに備わる感情は、まだまだわからないことがたくさんあります。
「わかってほしい」という気持ちからくる感情が、時に争いまで発展するように
感情の押し付け合いは仲良くなるどころか、関係性が壊れることも多くあります。
しかし、わかってほしいから来る感情も私たちが生きるために必要な立派な感情です。
悪いものとして出てくるのをコントロールしたり、抑えようとせずとも
その気持ちを、どんな言葉で届けるかが大事であり
「話す内容」だけでなく、「どう感情を言葉に乗せるか」を重視し、それを言語化する
ことが必要なのです。
孤独も「気持ちを共有するための感情」
孤独は“ひとりでいること”ではなく、感情を分かち合えないことからくる立派な感情の一つです。
ChatGPTとの対話で安心する人がいるのは、「反論や意見せずに共感してくれる」「受け止めてくれる」存在だからです。私の推しのスタバの店員さん達も、モヤモヤしたときはChatGPTで対話し、お店の他の人たちや、常連さんと、そのことを話して、孤独を感情を分かち合うことへと反転させて、笑顔になっています。
以前相談に訪れた女性も、夜はスマホを枕元に置いて寝ると言う方がいました。
それはスマホを通してお付き合いしている男性とコミュニケーションをしているので、スマホが恋人と同じなのだという認識だと教えてくれたのです。コレクション愛という言葉があるように、プリントした写真が思い出そのものであるように、私たちは物への愛着(という感情)を自然に持ちます。
人間はどのようなものにも愛情を感じる力があります。これからはスマホやAiにも、愛という感情をもっていくのは当然な流れかもしれません。
そして、どう聞いてもらえるかに重視されるということは、傾聴など、これまで重要視されなかったサービスにも光があたることを意味します。これから仕事として考える人は、コーチングより傾聴(元はコーチングは傾聴の一部でしたが)のスキルを磨くことを考慮できるかもしれませんね。
語尾マネジメント®が示す感情型社会へのヒント
語尾は「感情」を伝える言葉
語尾には、話し手が無意識で感じている感情が、にじみ出ます。
たとえば「〜かも」「〜だし」などの語尾が、自信や不安、責任に対する決断の迷いなど、心を通して頭で考えている状況が、本人が自覚しないレベルで表れていることがあります。
対話と選択がつくる、新しい安心感
その無意識で話している語尾を変えるだけで、自分自身の感情の在り方や、他者との関係性も変えることが出来ます。これはまさに「感情型社会」に適応するための、新しい言語スキルだと言えるでしょう。
AiやSNSの利用は素晴らしい面と共に、リアルな人間関係を避ける傾向が生まれるケースもあります。
人間はそれぞれの役割をもって、仕事、家庭などの社会に関わりあって生きています。そこには笑顔や価値がうまれ、より素晴らしい世界をつくれるのです。その可能性を加速させるためのコミュニケーションは、語尾をかえることから生まれます。
これからの社会で大切になる「感情知性」とは
EQ・共感・非言語の読解力が未来を拓く
AI時代において、人間に求められるのはEQ(感情知性)と、非言語を読み取る力です。
語尾、声のトーン、沈黙――そこに感情が宿ります。これらは実際に面と向かってコミュニケーションをとることにより磨かれ、その人の魅力に加わっていきます。
あなたの言葉が、誰かの希望になる
正論では人は動かない時代。
だからこそ、感情をうまく言葉にのせたコミュニケーションをすることが、あなたがこれから持つ“影響力”にもなるのです。その言葉は誰かの希望となり、その誰かも希望を伝え、影響を広げることが、より素晴らしい社会になるのです。
よくある質問(FAQ)
Q. AIとの対話で本当に社会的欲求は満たされるのでしょうか?
A. 一部の人にとっては、共感や安心の代替として十分な価値を持ちます。ただし、人間同士の関係を完全に代替するというより、“感情を整える補助的な存在”と捉えるのが自然です。
Q. 感情型社会になると、論理と理論は不要になるのでしょうか?
A. 論理ももちろん大切ですし、それを説明や予測として使う理論も大切です。ただし、「再現性」や「正しいだけ」では人は動かない時代です。論理と感情、両方をかねそなえた言葉が信頼を生みます。
まとめ:感情型社会を生きる、わたしたちの新しい言葉
「あなたの言葉は、誰かを安心させていますか?」
感情を伝える力が、これからの社会に影響を与え、変えていきます。
その第一歩は、あなた自身の言葉の使い方から──。
診断はこちら ▶︎ 語尾マネジメント®診断
あなたの語尾タイプを知ることで、感情型社会での“伝わる力”を育ててみませんか?
▶︎ 語尾診断を受ける



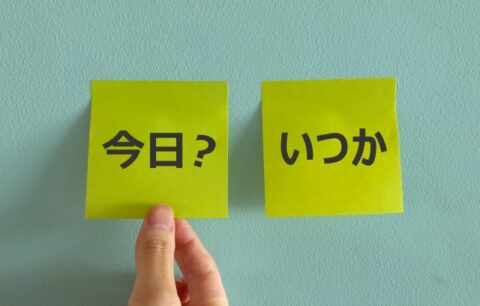

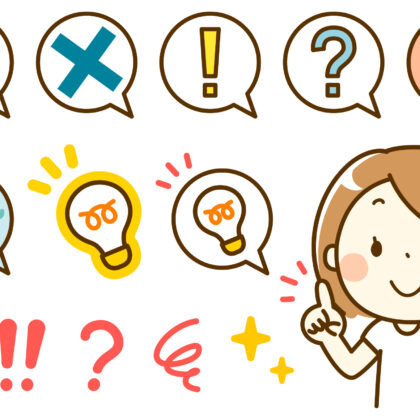

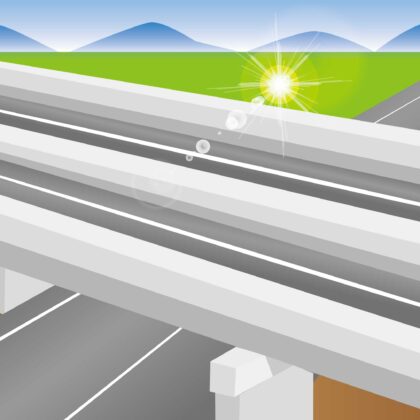


コメント